相続は「死後」ではなく「生前」にこそ準備するべき理由
多くの人が「相続は亡くなった後に遺族が手続きするもの」と考えていますが、それでは遅いのです。生前に準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、家族の負担を大幅に軽減できます。相続税対策だけでなく、「誰が何を相続するか」の意思表示や、財産の整理、負の遺産の把握など、やるべきことは山のようにあります。終活の一環として、自分の人生の幕引きを「自分で演出する」ことが求められる時代です。
自分でできる相続準備|最低限押さえておきたい5つのステップ
財産の棚卸しをする
まずは「自分が何を持っているのか」を把握しましょう。不動産、預貯金、株式、保険、貴金属、借金などを一覧にして書き出すことから始まります。見落とされやすいネット銀行口座や仮想通貨も注意が必要です。
相続人を確定する
配偶者、子ども、兄弟姉妹など、法定相続人は民法で決まっています。相関図を作り、誰がどの立場になるのかを把握しましょう。過去の婚姻歴や認知した子どもがいる場合は、より注意深く整理が必要です。
遺言書を書く
公正証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言でも法的効力はありますが、形式不備で無効になるリスクがあります。公証人と証人を立てて作成すれば、争いの芽を摘むことができます。自分の意思を確実に残すための最重要ステップです。
相続税の基礎控除と納税義務を確認する
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合、相続税が発生します。不動産評価や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)などをうまく使えば、節税も可能です。生前贈与を計画的に使うのも有効です。
デジタル終活も忘れずに
SNSアカウント、サブスクリプションサービス、暗証番号の管理など、死後に残される「デジタル遺品」もトラブルのもとになります。重要な情報は紙に残し、信頼できる人物に伝えておきましょう。
自分でできる範囲と専門家に任せるべき境界線
生前の財産整理や遺言書の作成は、自分でも十分対応できますが、税務処理や不動産登記、相続トラブルへの対応は、専門家の知見が必要です。税理士、司法書士、行政書士、弁護士、それぞれの得意分野を活用することで、スムーズな相続が可能になります。
家族が揉める最大の原因は「何も準備していなかった」こと
相続トラブルは金額の大小に関係なく起こります。特に「長男が当然にすべてを継ぐと思っていた」「母の介護をしていたのに何も相続できない」など、感情的な対立が原因になるケースが多いです。遺言書とともに、エンディングノートを残して、自分の思いや理由を丁寧に伝えることが争いを防ぐカギとなります。
いますぐ始められる!終活チェックリスト
- 財産リストを作成する
- 家系図・相続人リストをまとめる
- 遺言書のドラフトを作る
- 生前贈与の方針を検討する
- 保険の見直し・受取人の確認
- 不動産の名義を確認し、必要なら名義変更や売却を考慮
- 葬儀やお墓についての希望を記録
- SNSやネット銀行などのデジタル情報を整理
- 信頼できる相談先(税理士・司法書士など)を見つけておく
自分の人生の終わり方は、自分で決めていい時代
かつて「相続」は専門家に任せきり、「終活」は縁起でもない話と避けられていました。しかし今は、自分の死後に向けて「人生の最終章」をデザインすることが普通になっています。家族の笑顔と安心のために、そして自分の生き方にけじめをつけるために、相続と終活は避けて通れない人生のテーマです。何も残さず逝くより、準備万端で旅立つ方が、残された家族にとっても、なによりあなた自身にとっても、最良の選択なのです。
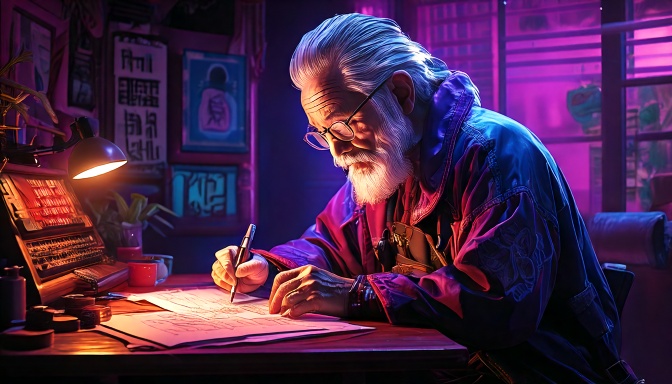
コメント