企業の会議や打ち合わせにかかる費用を「会議費」として処理してよいか、それとも「接待交際費」に分類すべきか――この判断は節税や税務リスクの観点から非常に重要です。令和6年4月の税制改正により、飲食を伴う会議費の扱いも変化しており、最新の基準を押さえておく必要があります。この記事では、会計処理における「会議費」の定義・基準・仕訳から、接待交際費との違い、税務調査対策までを詳細に解説します。
会議費とは何か?基本の定義と範囲
会議費とは、業務上必要とされる会議・打ち合わせを開く際に生じる費用を指します。これには、会場使用料・会議室レンタル代、資料作成費、プロジェクターレンタル、会議中の飲食・軽食代などが含まれます。(スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社)
ただし、この定義だけでは判断が曖昧になることが多いため、実務では以下のような観点が重視されます:
- 会議の目的・内容が業務遂行に直結していること
- 実際に会議という場が設けられていること(単なる飲食や懇親会ではないこと)
- 飲食代を伴う場合、その金額が社会通念上妥当であること
なお、会議費に関しては法律上「一定の金額上限」が定められているわけではありません(飲食以外の費用、会場費などには上限なし)(やよい軒)。しかし、飲食代部分には、接待交際費と区別するための金額基準が設けられています。
飲食費を会議費として処理できる基準(旧 5,000円基準 → 新 10,000円基準)
飲食を伴う会議費の取扱いにおいて、最も判定が難しいのが「飲食代を会議費として認めるかどうか」です。以下の基準が、税務上の判断における最前線になります。
旧基準:5,000円基準
これまで、飲食代が会議費として扱えるのは、1人あたり5,000円以下である場合とされていました。いわゆる「5,000円基準」です。(請求ABC)
ただし、5,000円以下であっても、すべてが会議費扱いになるわけではありません。飲食が「接待目的」であると認定されると、たとえ1人5,000円以下であっても交際費として取り扱われる可能性があります。(請求ABC)
また、この基準を適用するには、以下の記録保存要件を満たしておく必要があります:
- 実施日(飲食があった日)(経理プラス)
- 参加者の企業名・担当者氏名・関係性(経理プラス)
- 参加人数(実際に参加した人数)(経理プラス)
- 飲食店名・所在地・支払額(飲食分)(経理プラス)
- 会議開催が行われたことが分かる議事録や資料など(経理プラス)
新基準:10,000円基準(令和6年4月以降)
令和6年(2024年)4月の税制改正において、この5,000円基準が見直され、1人あたり10,000円以下まで認められるようになりました。(getmoneytree.com)
すなわち、飲食を伴う会議費について、従来の5,000円の制限が2倍に引き上げられ、1人10,000円以下なら交際費から除外して会議費として取り扱えるという扱いが認められるようになったのです。(日本橋人形町の相談できる税理士事務所 | 税理士法人ウィズ)
ただし、この新基準を適用するには、同様の記録保存要件が引き続き必要です。(経理プラス)
また、注意点として、社内のみの会議(取引先等の社外者なし)に対する飲食費については、たとえ10,000円以下であっても会議費としての適用外となるケースもあります。(superstream.canon-its.co.jp)
さらに、この10,000円基準は、税込経理方式か税抜経理方式かで判定基準の使い方が変わることにも留意が必要です。(日本橋人形町の相談できる税理士事務所 | 税理士法人ウィズ)
会議費と接待交際費の違いと区分ルール
会議費と接待交際費を明確に区分するためには、以下のような論点を整理しておく必要があります。
接待交際費とは
接待交際費とは、取引先・得意先・仕入先などの関係者を接待・歓待・贈答などによって関係強化・維持を目的とする支出のことです。(バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」)
この接待交際費には、法人税法上損金不算入の扱いがされる部分があり、課税所得との関係で慎重な扱いが求められます。(バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」)
主な区分ポイント
| 区分観点 | 会議費と判断されやすい条件 | 接待交際費と判断されやすい条件 |
|---|---|---|
| 主目的 | 会議・打合せ・意思決定・議論など | 接待・歓談・関係強化 |
| 飲食を伴うか | 飲食代が1人10,000円以下でかつ記録要件を満たす | 飲食代が基準を超える、または接待目的である |
| 参加者 | 社内および社外、業務関係者が参加 | 取引関係者、客先、場合によって親族等を招く |
| 実態 | 会議資料、議事録、会議場所、議論の記録がある | 単なる食事会、懇親が主となって内容が希薄なもの |
このように、勘定科目として「会議費」か「交際費」かを判断する際には、「実質」を重視することが重要です。形式や勘定科目の記載だけで判断がなされるわけではなく、実際にどのような目的・内容で支出がなされたかが最優先に評価されます。(タックスナップ)
実務における仕訳例と処理ポイント
会議費として処理する際の基本的な仕訳とポイントを押さえておきましょう。
仕訳例
たとえば、社外との会議で、会議室使用料 30,000円、資料印刷代 5,000円、飲食代(参加5人)で合計 25,000円(1人5,000円)だった場合:
| 借方 | 貸方 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 会議費 30,000円 | 現金(又は預金) 30,000円 | 会場使用料分 |
| 会議費 5,000円 | 現金 5,000円 | 資料印刷代 |
| 会議費 25,000円 | 現金 25,000円 | 飲食代(5,000円/人 × 5人) |
このように、すべてを「会議費」として計上しています。ただし、飲食代が1人5,000円を超えていたり、接待目的と認定されると、交際費扱いに切り替える必要があります。(スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社)
消費税の扱い
会議費の費用項目は、国内取引分に関しては**原則として課税対象(課税仕入)**になります。(Chouseisan)
ただし、海外で行った会議費については、消費税の課税対象外となるケースもあります。(Chouseisan)
また、株主総会のための会場費等も課税仕入として扱われます。(税金Lab税理士法人)
消費税の仕訳例(課税仕入対象)
会議用備品や会場費、飲食代すべてに消費税がかかっているとすると、例えば課税率10%と仮定した場合:
- 会場使用料 30,000円(本体価格 27,273円、消費税 2,727円)
- 資料代 5,000円(本体 4,545円、消費税 455円)
- 飲食代 25,000円(本体 22,727円、消費税 2,273円)
仕訳は次のようになります(簡略化):
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会議費 27,273円 | 買掛金等 | 27,273円 | |
| 仮払消費税等 5,455円 | 買掛金等 | 5,455円 | |
| (同じように資料・飲食も仕訳) |
こうして、課税仕入として消費税を控除できる形での処理になります。
税務リスクと税務調査で問われやすい点
会議費として処理していたものが、税務調査で「接待交際費」や「役員報酬・従業員給与」などと判断されるケースがあります。これには次のような注意点があります。(〖月額1,100円~〗バーチャルオフィス東京・銀座)
「会議の実体」がないと認定されるリスク
会議資料・議事録・出席者記録などがない、会議の目的が不明瞭、飲食主体で議論要素が薄いと判断されると、実際には会議でなかったとみなされ、交際費扱いや役員給与扱いをされる可能性があります。(〖月額1,100円~〗バーチャルオフィス東京・銀座)
私的飲食・表彰・慰労との混同
一部の支出が、会議とは無関係に従業員慰労・表彰・役員の個人的費用と認定されれば、費用性が否定され、損金不算入や所得税源泉の追加支払いを迫られるリスクがあります。(〖月額1,100円~〗バーチャルオフィス東京・銀座)
まとめて「会議費」で計上し過ぎていた場合の是正リスク
金額が大きいものや頻度が多いものを一括して「会議費」として処理していた場合、税務調査で精査され、交際費への振替を求められることがあります。これにより、追加の法人税や消費税を納付する必要が生じ得ます。(〖月額1,100円~〗バーチャルオフィス東京・銀座)
実務で注意すべきポイント・ベストプラクティス
- 会議費として処理すると判断するなら、議事録、出席者名簿、会議目的、会場や時間の記録などを確実に保存する
- 飲食代を伴う場合、1人あたり10,000円以下の金額に抑える(令和6年4月以降の基準)
- 税抜経理・税込経理方式により、基準適用の算定方法が変わるため、社内ルールを統一しておく
- 会議費として処理できないと判断される可能性が高い支出(接待色の強い会食、娯楽要素の強いもの)は交際費として正しく処理する
- 定期的に会議費処理ルールを見直し、経理担当者に教育徹底する
- 税務調査を想定し、説明できる実態を常に整理しておく
まとめ
会計処理における「会議費」の扱いは、節税と税務リスク回避の観点から非常に重要です。会議費として正しく処理するためには、**業務目的・会議実体・記録保存・金額基準(現在は1人10,000円以下)**といった要件を押さえ、しかるべき証拠を揃えておくことが不可欠です。これらを適切に運用することで、接待交際費の損金不算入リスクを避けつつ、会議費扱いの範囲を最大化することができます。
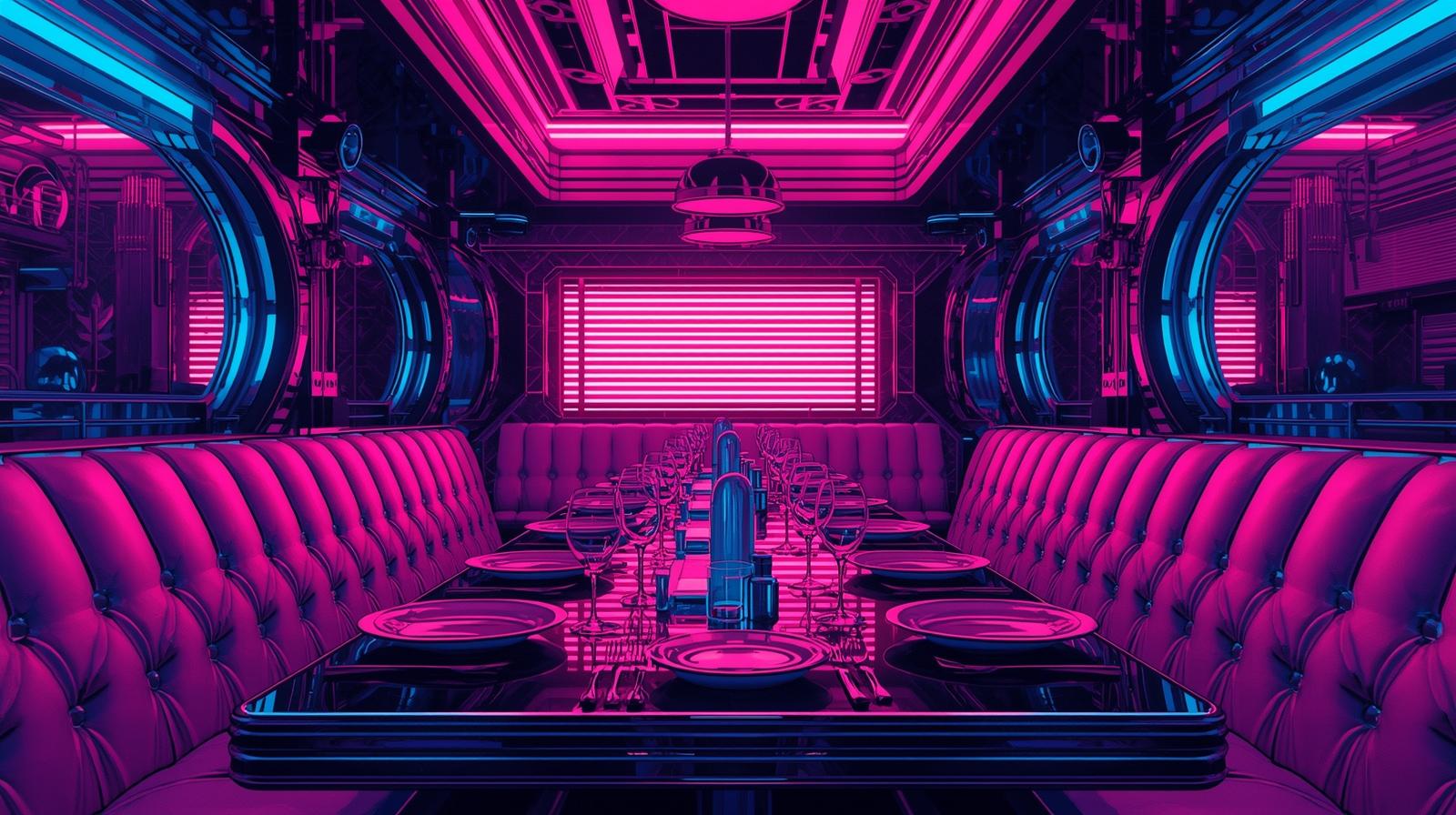
コメント